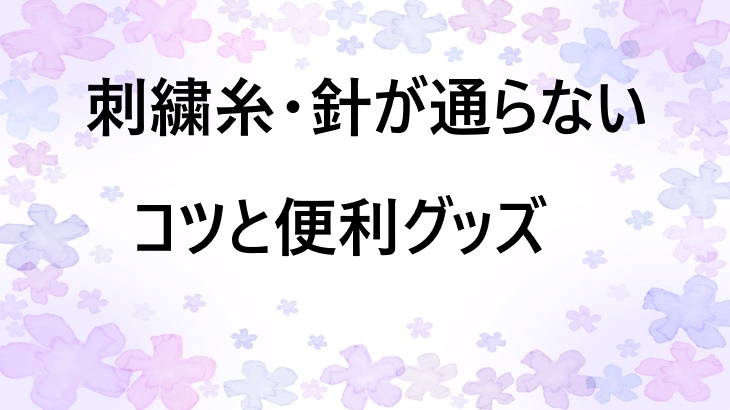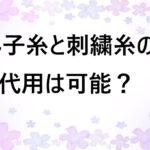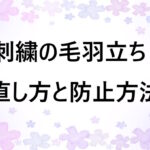この記事では、すぐに試せるコツと、糸通しが楽になる便利アイテムを紹介していきます。
「刺繍糸が針に通らない…!」これは裁縫や刺繍をしたことのある方なら一度は感じたことのあるプチストレスではないでしょうか。
針に糸を通すという、たったそれだけのことで作業が中断してしまいます。小さなことなのですが、それが毎回何度も続くと、刺繍道具を出すのもめんどうになってきて、「もうやめようかな…」と。気がついたら途中まで作った刺繍キットが何ヶ月も放置されている…、ということも…。
そんな小さなストレスを少しでも減らすことができるよう、この記事では・刺繍糸を針に通すちょっとした「コツ」と便利な道具の活用方法を紹介します。
「刺繍をもっと楽しく」「ストレスなく続けたい」そんな方はぜひ参考にしてください。
刺繍のちょっとしたコツをまとめて知りたい方はこちらの記事にまとめてあります。
>>> 刺繍をもっと楽しむコツまとめページ
✨ もっと知りたい方へ
刺繍の道具選び・糸の違い・作品の飾り方までをテーマ別にまとめた「刺繍情報まとめページ」をチェックしてみてください。
刺繍糸が針に通らない:最初に試したい3つの方法
まずは「とにかく今すぐ何とかしたい!」という方に向けて、すぐに試せて効果が出やすい方法を3つ紹介します。
1. 糸先を斜めにカットする
まず基本中の基本は、糸の先端を整えること。刺繍糸は6本〜8本の細い糸が束になって1本になっているため、切り口が乱れているとバラけて通しにくくなります。
作業の前に、糸先をハサミでまっすぐスパッとカットしましょう。ほんの数ミリでも、切り口が整うと格段に通しやすくなります。
特に、糸を2本取りや3本取りにして使う場合は、糸が柔らかく広がりやすいので、この方法が効果的です。
おすすめは手芸用のハサミ。クラフト用よりも刃先がシャープで、毛羽立たずきれいに切れます。
私も手芸用のハサミを購入してから、糸の先端を切る作業が格段に便利になりました。家にいくつかあるハサミですが、手芸専用のハサミを使ってみたら、通常のハサミには戻れなくなりました。裁縫用、手芸用のハサミが1本あると便利ですよ。
2. 糸通し器を使ってみる
細かい作業が苦手な方や、目が疲れやすい方には糸通し器がおすすめです。針穴にワイヤーを差し込み、そこに糸を通して引き抜くだけでOK。
不器用でも視力に自信がなくても、スルッと糸が通ってくれる心強い味方です。
ワイヤータイプの刺繍専用糸通し器もおすすめです。柔らかいワイヤーが針穴にスッと入って、糸を引っ張るだけで簡単に通せます。
こちら↓は刺しゅう専用の糸通しです↓
3. 専用の刺繍針に変える
実は意外と見落とされがちなのが「針の種類」です。手元にあった針をそのまま使っていませんか?
刺繍用の針は、刺繍糸が通りやすいように穴が大きめに設計されています。
中でも「フランス刺繍針」や「クロスステッチ針」は、糸の本数や用途に合わせて選べます。
針を変えるだけで驚くほど通しやすくなるので、ぜひ一度チェックしてみてください。
刺繍針です↓
針にスッと通す!刺繍糸の通し方・コツ
刺繍糸を針に通すときの工夫、「コツ」をご紹介します。
うまく針に糸が通らないときは、ひとつずつ試してみてください。
上記でご紹介した方法と似たやり方も含まれますが、順番に説明していきます。
1. 糸がバラけて通らない!まずは「まっすぐカット」で整えよう
刺繍糸は6本〜8本の細い糸が束になってできているため、切り口が少しでも乱れているとすぐにバラバラになります。
作業前に、糸先をまっすぐスパッとカットして整えましょう。
数ミリの差ですが、驚くほど通しやすさが変わります。
おすすめは手芸用の細かい刃のハサミ。普通のハサミよりシャープで、糸の毛羽立ちも防げます。
裁縫・刺繍用の糸切りハサミです↓
2. まっすぐカットでもダメなら「斜めカット」
「まっすぐ切ったのに、それでも通らない…」というときは、斜めにカットしてみてください。
先端が尖ることで、針穴にスッと入りやすくなるんです。
特に2〜3本取りで使う場合は、糸が柔らかくなって通しづらくなりがち。
そんなときは、斜めカットを試してみてください。
3. 細かい作業が苦手なら「糸通し器(スレダー)」
「指先がうまく動かない」「針穴が見づらい」「もう何度もチャレンジして疲れた」
そんな方には、糸通し器(スレダー)という便利グッズがピッタリ!
刺しゅう専用の糸通し器です↓
4. 糸が広がる・まとまらない時は「湿らせるorワックス」
糸の先がふわっと広がって通らないときは、少しだけ湿らせるとまとまりやすくなります。
指先を水で軽く濡らして、糸の先を整えるだけでもOK。
例えば、ウェットティッシュで少し指先を湿らせる、事務用のスポンジを使うなどでも代用できます。
指を湿らせることが目的なら、このような事務用スポンジでも代用できます。↓
ただ、衛生面や糸の劣化が気になる場合は、刺繍用ワックスを使うのがおすすめ。
糸に軽く塗るだけで、まとまりがよくなり静電気も防げます。乾燥する季節や長時間の作業にも最適です。
糸の先にひと塗りするだけで、糸がしっかりまとまり、静電気も抑えてくれる優れモノです。
クロバー(Clover)の糸ワックス↓も使いやすいです。
糸ワックスは、刺繍糸がねじれたり絡まったりするときにも便利に使うことができます。詳しく知りたい方は下記の記事も参考にしてみてください。
>>> 刺繍糸がねじれる、絡まる、よれるのを防ぐ方法と対策!便利アイテムも紹介
5. 糸が太くて入らない…なら「本数の見直し」も考えてみる
刺繍糸を分けて使うとき、何本取りにするかによって通しやすさが大きく変わります。
たとえば、3本以上にすると太くなり、針穴に入りづらくなります。そんな時は、通しやすいように1〜2本ずつ分けておき、あらかじめまとめて整えてから通すのがコツ。
手のひらで優しく転がしたり、ワックスを塗るなどして、糸がバラけないようにしましょう。
6. 針を刺繍用に変えてみる
意外と盲点なのが、そもそも使っている針が刺繍用ではないというケース。
手元にある針をなんとなく使っている方も多いですが、刺繍針は穴が大きめに作られていて、刺繍糸を通しやすく設計されています。見た目は似ていても、使いやすさがまったく違うので、一度試してみてください。
中でも「フランス刺繍針」や「クロスステッチ針」など、用途に合わせたものを選ぶと◎。
クロスステッチ用の針はこちら↓
フランス刺繍針はこちらです↓
7. 針穴が見えない!「ライト」や「拡大鏡」を使う
案外見落としがちですが、作業中の明るさも大切。針穴が小さいと、影になって見えにくくなるんです。
自然光の下や、手元ライトを使って、しっかり明るさを確保しましょう。目の負担も減って、集中力も続きますよ。
下記は読書の時などにも使えるクリップライトです↓。手芸や刺繍をしている作業机は、意外と材料や道具でスペースが足りない場合が多いです。クリップタイプなら、机のスペースを有効に使うことができますよ。
明るさの調節もできます↓
手芸や刺繍のときに便利な拡大鏡(ルーペ)について、もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。
>>> 手芸や刺繍に便利なルーペの種類を紹介!ルーペ(拡大鏡)を選ぶポイントも解説
下記のようなルーペを使うと、格段に見やすくなります↓
そもそも、なぜ刺繍糸は針に通りにくいの?
そもそも、なぜ刺繍糸は針に通りにくいのでしょうか。
糸の構造による「広がりやすさ」
刺繍糸は、6本〜8本の細い糸が撚(よ)られて1本になっているため、切り口がとてもデリケート。
一度ほぐれ始めると、あっという間にバラけてしまい、針穴に通すのが難しくなります。
さらに、糸を数本に分けて使う「2本取り」「3本取り」などをすると、まとまりが弱くなり、ますます通しづらくなります。
この“広がりやすさ”をカバーするには、先端をきれいにカットする・ワックスを使うなど、糸を整える意識が大切です。
糸ワックスです↓
針の穴との「相性の悪さ」
意外と見落とされがちなのが、「針と糸の相性」です。家庭にある縫い針は、通常のミシン糸用に作られており、穴が小さめです。
そこに刺繍糸のような太めの糸を通そうとしても、物理的に入りづらいのは当然で、どんなに糸先を整えても、針が合っていなければ苦労するだけになってしまいます。
刺繍には、針穴が広めに作られた「刺繍専用針」を使うのが基本。用途に合った針を選ぶだけで、通しやすさはぐんとアップします。
刺繍用の針です↓
糸の状態が悪いまま使っている
何度も触っているうちに糸先が毛羽立ったり、床に落としてホコリがついてしまったり…。
こうしたちょっとしたことで、糸はどんどん状態が悪くなっていきます。
また、湿気や手汗などで糸が柔らかくなり、まとまりがなくなることも通しにくさの原因に。
刺繍前には、必要な分だけをカットして、できるだけきれいな状態で扱うのが理想です。
状態が悪くなった糸は、思い切ってカットして整え直すことも大切。
「もったいない」より「スムーズに進める」ほうが、刺繍はずっと楽しくなります。
できれば下記のような手芸用ハサミを使うと◎↓
まとめ
「刺繍糸が針に通らない」――それだけで作業が止まってしまうと、本当にストレスですよね。
でも、今回ご紹介したように、糸先のカット方法や道具の力を借りることで、その悩みはグッと軽くなります。
特に効果が高いのは、斜めにカットする・糸通し器を使う・刺繍専用針に変えるという3つの方法。
この基本を押さえるだけでも、刺繍がずいぶんスムーズになります。
さらに、糸の状態を整えたり、手元を明るくしたりといったちょっとした気配りも、作業効率アップのカギ。
糸が通りやすくなると、集中力も高まり、刺繍そのものがもっと楽しくなってきます。
小さな「つまずき」を解消することで、刺繍の時間はもっと快適に、もっと心地よく変わります。
ぜひ、今回のコツやアイテムを取り入れて、あなたらしい刺繍時間を楽しむ参考にしてみてください。
他にも刺繍関連のコツ、ミシン・編み物関連のアイデアを読みたい方は、こちらの記事もあわせて参考にしてみてください。
>>> ハンドメイドのコツ&アイデアまとめページ
他にも気になることがあれば、刺繍に関するヒントをまとめたページがあります。
気になるテーマをチェックしてみてください。